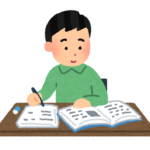夏休みを制する!東進大垣高屋校
夏休みは勝ち癖を付ける絶好のチャンス
夏休みは「受験の天王山」とよく言われます。確かに、まとまった勉強期間が取れるこの期間をどう使うかで、今後の成績が大きく変わるのは事実です。
ただ、意外なことに、この“天王山”で多くの受験生が失敗しています。
その理由はシンプル。「夏休みはたくさん時間があるから大丈夫」と油断してしまうからです。気づいたら勉強が思うように進んでいなかったり、部活や遊びに引っ張られてしまったり。気づいたときにはもう夏が終わっていた...という後悔を、多くの先輩がしています。
でも、逆に言えばしっかり計画を立てて、日々を改善しながら過ごせば、それだけで一歩も二歩もリードできるということです。
勝ち癖を付けるという考え方
夏休みは「失敗しないようにする」ではなく、「小さな成功体験を積み重ねる」期間だと考えてほしいです。
成功と言っても、模試の点数のような大きな結果ではなくて構いません。
「一週間で決めた範囲をやり切った」「今週は毎日英単語を30分続けられた」そんな小さな達成感でOK。
大切なのは、自分で決めたことを実行して、それを認めてあげることです。
ただし、「勝ち癖」は感覚ではなく、客観的に評価することが必要です。つまり、振り返りと改善です。
夏休み成功に鍵は「改善サイクル」
まずは、夏休みのはじめに目標を立てましょう。その上で、「週ごと」に振り返って改善する「サイクル」を回すのがポイントです。
例えば、「数学で青チャートの例題を2週やる」という目標を立てたら、1週間後に「できたか?」「ペースはあっているか?」「もっと重点を変えるべき?」と振り返る。
その上で、次週の方針を修正します。
こうして、自分の基準や行動をどんどんアップデートしていくことで、自然と「勝てるサイクル」ができていきます。
科目別勉強戦略~「コツコツ型」と「成績比例型」~
勉強内容は大きく2種類に分けて考えると効率的です。
【コツコツ型】
英単語・熟語、リスニング、古文漢文など。
これは毎日短時間ずつ積み重ねるのが効果的です。
例えば移動時間、昼休憩、寝る前など、15分単位の隙間時間で取り組むと継続しやすいです。
おすすめは、「ランダムリフレクション」。例えば青チャートのページをランダムに開いて、その問題の解法がすぐに浮かぶかをチェック。
これも毎朝15分でできる、非常に効果的な方法です。
【成績比例型】
数学、理科、社会などは、やった分だけ力が伸びやすい科目です。
特に数学Ⅲは差がつきやすいので、時間をかけてじっくりやるべき科目。
勉強時間の組み立て方~15分・1時間・無制限~
1日の中で勉強を「3つの時間スケール」に分けて考えましょう。
・15分:隙間時間
英単語・熟語、リスニング、古文漢文、ランダムリフレクション
・1時間:集中して取り組む系
英語長文、英文解釈、現代文など
・unlimited(3~4時間):メイン学習
数学や理科の演習、過去問など
朝9時~12時のブロックなど、長時間集中して取り組みます。
疲れたら15分系の軽い勉強を挟んで、またunlimitedに戻る。このリズムを作ると1日12~13時間の勉強も無理なく続けられます。
夏休み計画の三原則
- 「締め切り」と「環境」のメリハリをつける
週間ごとに目標と締め切りを設ける。
「今週はここまでやる」と決め、それを達成できたかを振り返る。
更に、勉強場所にもメリハリを。家でだらけてしまうなら図書館や自習室を活用
- 模試の「準備日」と「復習日」を確保する
模試の翌日は必ず半日~一日かけて復習。
受けっぱなしでは意味がありません。 模試も本番と同じように調整→実施→振り返りというサイクルを回すことで、実力が本当に伸びます。
- 理想基準は「タスク達成」、最低基準は「勉強時間」
勉強時間を「最低基準」として守るのは当然ですが、最終的に目指すのは「タスクの達成」です。
・受験生:一日10時間(できれば12~13時間)
・高1・2生:一日7~8時間(できれば9~10時間)
これは必ず達成してください。タスクに関しては、出来なかった週があっても、反省して翌週改善すればOK。完璧な計画など存在しません。
大事なのは「改善サイクルを止めないこと」です。
最後に
夏休みが終わったとき、「やり切った」と胸を張って言えるかどうか。
それは、今ここからの行動次第です。
隙間時間を制する者は受験を制す。
自分で立てた計画を、一つずつ丁寧にクリアしていくことで、勝ち癖がつき、いつの間にか自信に代わっていきます。 夏は一度きり。悔いのない夏を過ごしましょう。